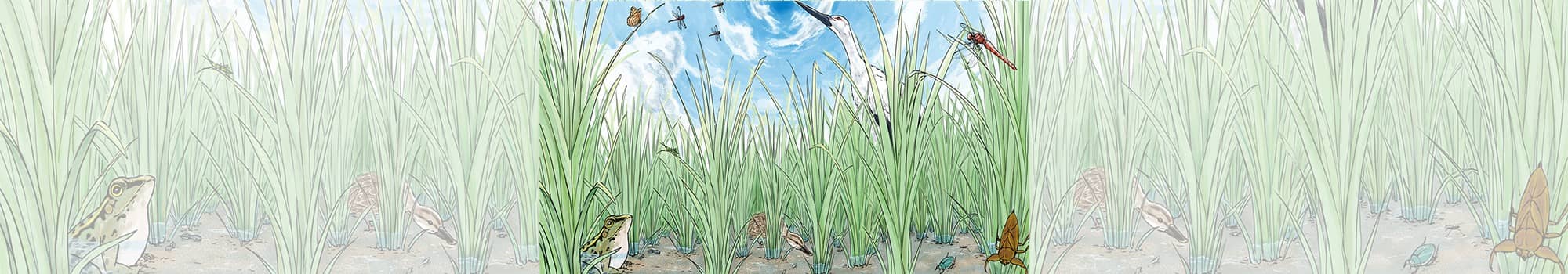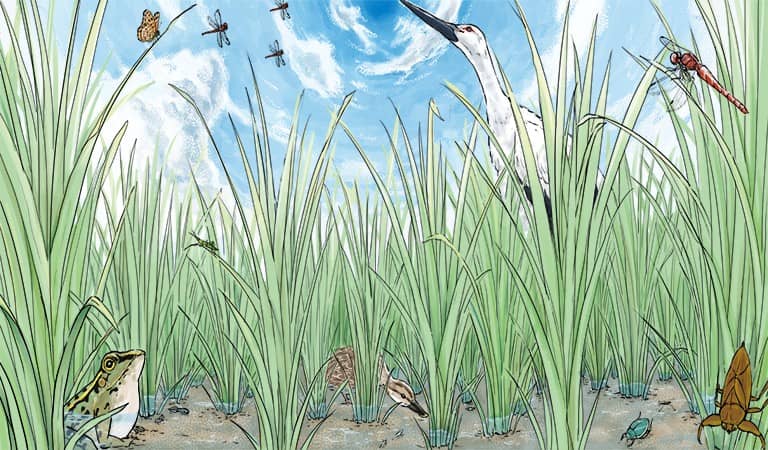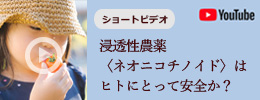高瀬毅『「ナガサキ」を生きる――原爆と向き合う人生』(亜紀書房/2025)
一般社団法人アクト・ビヨンド・トラスト代表理事 星川 淳
戦後80年の節目に、妻と二人のマイプロジェクトとして原爆と被爆の問題に、これまでより深く目を向けようと話し合った。人類史上、実戦被爆はいまのところ広島と長崎だけだし、私自身、1952年生まれで直接の戦争体験はないものの、両親を含む体験者たちから直接話を聞きながら育った最後の世代として果たすべき責任を負うにもかかわらず、そろそろ残り時間が見えてきた年齢も関係する。
とはいえ、ここ15年ほど事実上の本業となった市民活動助成の仕事では、それなりにできることはやっており、そのほかに離島から個人として何が可能かを考えると、数多い既存の取り組みに寄付するとか、そのどれかにリモートでボランティア参加するとか、選択肢は限られる。そこでとりあえず、原爆・被爆をテーマとする資料類で、書き手として改めて紹介したいものを取り上げることにした。今回はその第一歩だ(ただし、この後のシリーズでは必ずしも原爆・被爆の問題だけでなく、広く戦争を防ぐというテーマにも触れるだろう)。
なお「非戦ノート」というタイトルは、同い歳なのに先立ってしまった坂本龍一さんを中心とする仲間たちと合作した『非戦』(幻冬舎/2002)を踏まえ、坂本さんの遺志を多少なりとも継いでいきたい気持ちも込めている。
人体実験
ジャーナリストの高瀬毅さんによる最新刊『「ナガサキ」を生きる』は、大きく分けて2つの主題を扱っている。1つは、なぜ2発目の原子爆弾が長崎に投下されたのか。もう1つは、高瀬さんが報道の先達として心の師と仰ぐ故・伊藤明彦さんの仕事だ。前者は、ある意味でマニアックな追究ぶりだが、原爆投下をめぐる詳細や新事実は、将来の核兵器使用に歯止めをかける手がかりになるかもしれない。そして後者は、使命を強く自覚したジャーナリストが、それを生きざまとして貫いたとき何ができるのかを、ほかに例を見ないような形で私たちに突きつける。
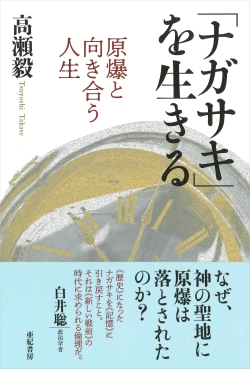
そこでまず、広島に投下されたものとは構造の異なるプルトニウム型原爆が、長崎の浦上地区に投下された経緯について、本書から私が知らなかったことを中心にご紹介する。
1945年8月9日早暁、中部太平洋マリアナ諸島のテニアン島を飛び立ったB29「ボックスカー」が、北九州の小倉を本来の標的としていたことは周知の事実だろう。しかし、投下目標が長崎に変更された理由や、その変更が再度、現地上空で微修正された事情は、諸説あるものの確定的な情報は存在しない。それどころか、本書によると米政府・米軍関係者のあいだでも記憶や見解が分かれ、何かを隠そうとしているようにさえ見えるという(陰謀説の類ではない!)。
当日、原爆搭載機+爆撃効果計測機+撮影記録機という3機のB29で構成される爆撃チームは、2つの重大アクシデントに見舞われていた。1つめは、肝心の原爆搭載機の予備燃料用ポンプが故障して、2000リットルもの燃料が使えない状態で離陸せざるをえなかったこと。2つめは、3機の待ち合わせ場所だった屋久島上空で3番機(撮影任務)が合流できず、2機だけで小倉へ向かったこと。合流を待つあいだに、ただでさえ不足気味の燃料を浪費した原爆搭載機は、航続距離の余裕がほとんどなくなっていたのだ。これが長崎投下への伏線となる。ちなみに、広島の原爆投下に際しては激戦地で知られる硫黄島上空が合流地だったが、8月9日は台風の影響を避け、目的地の九州方面で空からも高い山々がランドマークとなる屋久島を目印に選んだとされる。
一方、定説では原爆投下候補地は当初、京都・広島・小倉・新潟の4都市だったところ、戦後処理を見据えたヘンリー・スティムソン陸軍長官が日本国民の懐柔のために京都を温存すべしと主張し(天皇制を温存したのと同じ理由)、替わりに長崎が加えられたことになっているが、実際には京都は最後まで3発目の原爆の最有力目標だったともいわれる。原爆投下の対象となる都市は無傷であることが望ましいとされ(新兵器の破壊力がわかりやすいから)、4つの候補地はいずれも基本的に東京大空襲のような大規模爆撃を受けていない。また、小倉と長崎の近郊には連合国側の捕虜収容所があり、それに配慮して広島が第1候補地に浮上したようだ。いずれも、「京都の文化遺産価値」などほとんど顧みない冷徹な判断に見える。
日米ともに総力戦を遂行していた以上、冷徹さはさておき、大きな要素は、米国が戦後の覇権争いを見通したとき、原爆の開発と実戦使用における圧倒的優位をソビエト連邦に見せつける必要があったことだろう。とりわけ、プルトニウム型原爆はウラニウム型より原料が入手しやすく(※)、威力も1.3倍大きい反面、技術的に難しいため(プルトニウム型の起爆計算用に開発されたのがコンピュータの始まり)、マンハッタン計画の目玉となり、7月16日のトリニティ実験成功も踏まえて、是が非でも実戦使用したかったのだ。これも長崎投下へのもう一本の伏線と考えられる。一方、ソ連側もスパイを通じマンハッタン計画の動向を把握しており、米英ソ3首脳が第二次世界大戦の戦後処理を話し合うポツダム会談の最中、7月24日にトルーマン大統領から原爆実験の成功を知らされたスターリンは、落ち着いた様子だったという。
(※著者の高瀬さんはこう書き、ウラニウム型の原料であるウラン235の抽出には手のかかる濃縮過程が必要なのに対し、プルトニウムは原子炉を動かせば使用済み核燃料から得られることを根拠にしているが、原子炉の燃料もウラン235なので、理屈がよくわからない。広島型は62kgのウラン235のうち2%足らずしか核分裂を起こさなかったのに対し、長崎型は6.2kgのプルトニウム239の16%が核分裂したという効率の差において、後者が優位に立つことを指すのかもしれない。また、広島に投下されたウラニウム型原爆は試験的な原子炉での臨界実験しか経ていないぶっつけ本番だったのだが、被爆当時の推定人口35万人とされる広島市民を実験台にしたことになる!)
小倉から長崎へ
第1目標の小倉には3度投下が試みられた。ところが、天候は攻撃を中止するほど悪くないのに煙がひどく、投下ボタンを押す爆撃手がどうしても目標地点を捉えられない。価値ある原爆は、レーダー爆撃ではなく目視で投下するよう厳命が下っていたのだ。この煙には諸説あり、1)隣接する八幡地区を襲った前夜の大空襲による火災の燃え残り、2)それに加えて、八幡製鉄所から各戸に払い下げられたコークスに火がつき、9日当日もくすぶっていた、3)広島の次は小倉だと推測した八幡製鉄所の幹部が従業員に指示し、コールタールを焚いて煙幕を張った――真相はわからないが、それぞれ日本側の証言者がいる。
一方、原爆搭載機と2番機(爆撃効果測定任務)の搭乗員による証言では、それでも2度目、3度目の投下を試みようとしたところへ、高射砲と、さらには戦闘機(零戦が10機ほど)の迎撃が始まったため、ついに投下を断念せざるをえなかったという。しかし、日本側の関係者や目撃者の証言では、無条件降伏間際の当時、高射砲はB29の飛行高度まで届かず、零戦を含むなけなしの残存戦力は本土決戦用に温存する方針で(戦闘機の場合、掩体壕と呼ばれる分厚いコンクリート製の偽装格納庫でも守りきれなければ朝鮮半島へ退避させたりしていた)、たった2機のB29を迎え撃つことなど考えにくかった。著者の高瀬さんは、総合的に判断して「何か説明したくないこと、隠したいことが日米両方にあるように思える」と記す。
とにかく、ボックスカーの機長は急遽、投下目標を長崎に変更する。第2目標を新潟とする案もあったが、前述のとおりギリギリの燃料でテニアンどころか沖縄まで戻れるかどうかも危うい中、選択肢は帰路に近い長崎しかなかったのだ。ところが長崎上空へ達すると、あらかじめ設定済みの目標地点(長崎市内中心部、中島川にかかる常盤橋付近)は雲に覆われて目視できない。かといって、原爆を積んだまま帰還することなど絶対に許されない。しかたなく厳命に背(そむ)いて、当初の目標地点へレーダー投下する手順に入ろうとしたそのとき、北西へ3㎞あまり離れた浦上地区が雲の切れ間から見えた。浦上地区には三菱重工業長崎兵器製作所などの軍需工場が連なり、原爆投下作戦上は長崎の第2目標とされていた。最後の瞬間にそこが目視できたことで、今日知られる長崎の被爆状況が決まってしまった。逆にいえば、長崎市中心部はかろうじて直撃を免れた。当初の計画どおりに投下されていたら、被爆2世である高瀬毅さんは母親もその親族もほぼ直撃を受け、この世に生を受けられなかったはずだという。
米軍関係者の内々で、長崎への原爆投下は失敗とみなされたらしく、高瀬さんのジャーナリスト感覚に「何か隠したいことがある」と匂うのは、米側に煮え切らないものがあるからではないか。おそらく“失敗”とは、ウラニウム型より威力が大きいはずのプルトニウム原爆を、実証条件の揃った小倉に投下できず、条件の劣る長崎市中心部へと目標変更した上、さらに地形の悪い浦上地区へ落としたために、1945年末までの推定で広島の犠牲者が約14万人だったのに比べ、長崎は約7万人にとどまったことを指すのだと思われる(建物の被害も起伏に富んだ長崎のほうがずっと少なかった)。「投下をしくじって被害が十分でなかった」というのは、被爆国の私たちからすれば非道極まりない勝者の奢(おご)りであり、いつか核兵器による民間人の大規模かつ無差別の殺傷が最悪の戦争犯罪と認定される際、こうした人体実験的な評価基準は厳しく裁かれなければならない!(ただし、このことはアジア太平洋戦争で大日本帝国が犯した多大な加害を免罪するものではない。)
知られざる偉業
戦後80年にあたる2025年8月、NHKの特別ドラマ「八月の声を運ぶ男」をご覧になった人もいるだろう。主人公のモデルが伊藤明彦さんだ。冒頭で触れたように、本書の著者である高瀬毅さんは、放送記者3年目の25歳にして伊藤さんに出会い、強い影響を受け続けた。前年の1979年夏、朝日新聞に掲載された伊藤さんについての記事がきっかけだった。元NBC長崎放送の記者で、会社を辞めてアルバイトで生計を立てながら単身、広島・長崎はもちろん全国の被爆者を訪ね歩き、その声を録音テープに記録する。8年間で収録した声は約1,000人(取材は2,000人に申し込んで半数に断られた)。高瀬さんには衝撃だった。
「さいごの被爆者が地上を去る日がいつかはくる。その日のために被爆者の体験を本人自身の肉声で録音に収録して、後代へ伝承する必要があるのではないか。被爆地放送関係者が歴史にたいして負うた責務ではないか」――伊藤さんは著書の一つ『原子野の「ヨブ記」』(径書房)にこう記す。そして、その責務を生涯にわたり誠実に果たそうとした。
手始めは、伊藤さんが企画し、1968年に放送開始したNBC長崎放送のラジオ番組『被爆を語る』だった。当初は1回あたり6分の番組が週3回。その後、週1回の5分に短縮されたものの、なんとこの番組は現在も『長崎は証言する』と改称して続き、報道記者の性根を鍛える場となっているそうだ(同局ではすべての記者が一度はこの番組を担当する)。番組担当経験のある記者の一人は次のように語る。「被爆者に話を聞くことからスタートするので、調査報道でも被爆者の体験に軸足があるんです。皆、見事にブレない。妙な方向には絶対に行かないんです」
ところが、番組開始からわずか半年で、伊藤さんは佐世保支局へ異動させられてしまう。労働組合委員長でもあった伊藤さんが、社の懐柔工作を受け入れないことの報復人事だったらしい。翌年には潔く退社して、退職金で録音機を買い込み、全国の被爆者を訪ねる取材に乗り出した。早朝と深夜は薄給の肉体労働、夜は飲食店で働き、日中を取材に充てた。収録した1,000人の声からとくに印象的な話をカセット(一部オープンリール)にまとめ、1989年から92年にかけて、公共図書館、大学・高校の図書館など合計900か所に寄贈する。テープの数にして1万3000本あまり。その後、284人の被爆者の声で構成する長編ドキュメンタリー『ヒロシマ ナガサキ 私たちは忘れない』を制作し、2006年にCD9枚のセットを再び全国の公共施設に収めた。
現在、伊藤さんが収録した被爆者の証言は、インターネットサイト「被爆者の声」で聴くことができる。伊藤さんは途中から映像記録にも着手し、ビデオ版も265人分が残されている(これも同サイトで視聴可能)。伊藤さんの晩年、同サイトの運営・管理を担当していた古川義久さんは、「伊藤さんの残した記録、とくに音声は被爆からあまり時間が経っていない時に録音しているので迫力があります」と語った。本稿の主目的はこのサイトを少しでも多くの人に知ってもらうことにあり、私自身も時間をかけて録音・録画内容をしっかり受けとめたい。また古川さんによると、伊藤さんは「米ロ英仏中の核保有国の各国の言語による発信もしたい」と考えていたようで、被爆者9人分、合計35本の英語による証言動画が、「被爆者の声」サイトからリンクされたYouTubeチャンネルで視聴可能だ。もっと多くの証言を、もっと多くの言語で届けられないものか――。
一人のジャーナリストが孤立無援でこれほどの偉業を成し遂げたことに最大限の敬意を表したいし、その仕事がほとんど埋もれてきた事実に、知らなかったことの反省を含め私も背中を押された。じつは、その伊藤さん自身も入市被爆者で、被爆直後の8月下旬に故郷の長崎へ戻り、晩年、慢性病で入院生活を送るようになって被爆との関係を意識したという。ついでに触れると、被爆2世である本書の著者・高瀬さんも、弟を膵臓がんで亡くしてから、歯科医で知らされた前歯の欠損が、被爆者の家系に有意に多い「先天性欠如歯」かもしれないと自覚し始めたそうだ。
本書はここで取り上げたほかにも、長崎の被爆とキリスト教との関係、広島の平和記念公園とハワイのパールハーバー国立記念公園との「姉妹公園協定」(2023年)に対する強い違和感など、高瀬さんならではの取材成果と考察が詰まっているが、すべてはご紹介しきれない。ぜひ、一読をお勧めする。
最後に、本書冒頭で、高瀬さんが伊藤さんと初対面の頃、高村光太郎の「冬の言葉」を示されて深く嚙み締めたという一節と、「あとがきにかえて」の結びに、伊藤さんの著書『未来からの遺言』(岩波現代文庫)から抜粋された一節(ある作家からの孫引きらしい)を並べてみる。これら2つの言葉のあいだに、伊藤さんの人生があり、高瀬さんの探究があるのだろう。翻(ひるがえ)って自分はどうか……その問いが読後の胸に木霊(こだま)する。
冬は鉄碪(かなしき)を打って叫ぶ、
一生を棒にふって人生に関与せよと。
* * *
死者を死せると思うなかれ
生者のあらんかぎり
死者は生きん