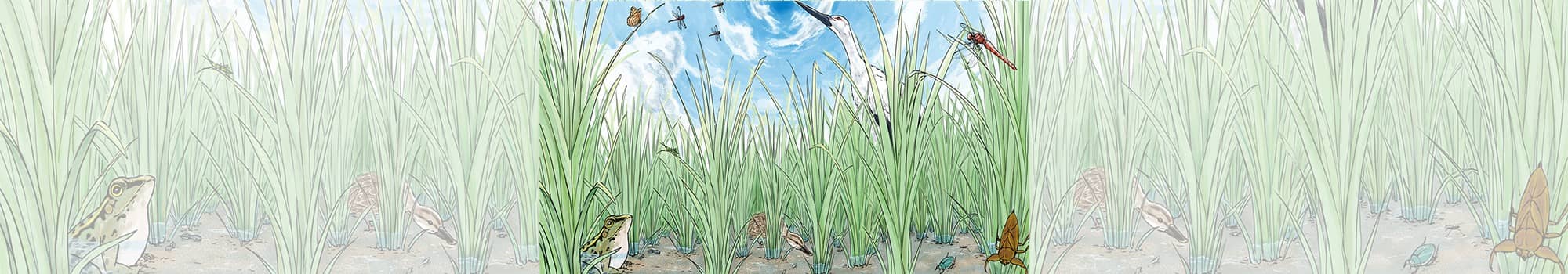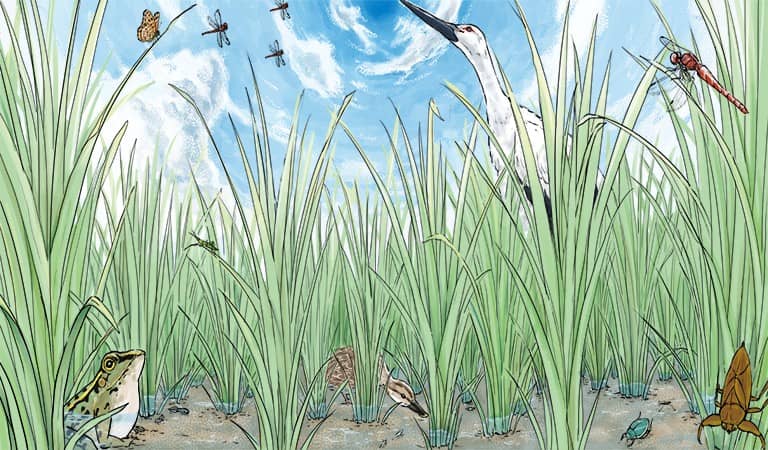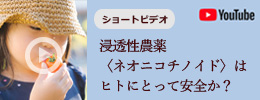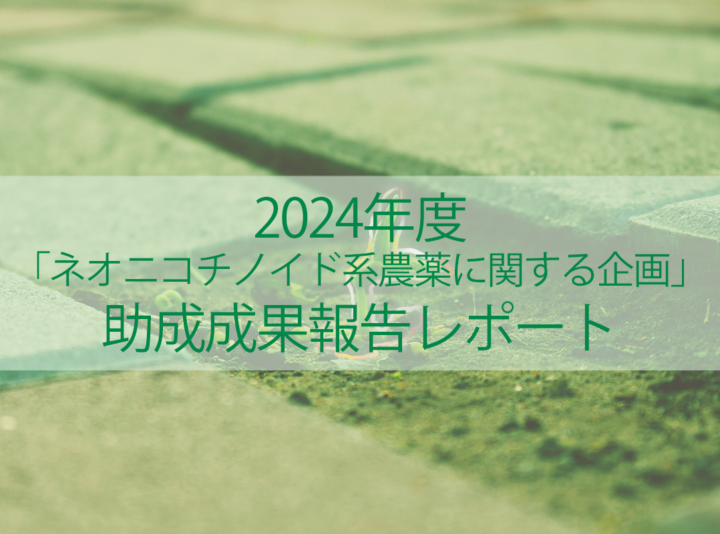
- 特定非営利活動法人・西日本アグロエコロジー協会
農家と消費者の参加型調査による農薬の圃場生態系への影響比較(2024) - 神戸大学大学院 農学研究科 動物分子形態学分野 星研究室
父性曝露影響から捉えるネオニコチノイド系農薬の継世代影響評価・エピゲノム毒性 - 秋田の環境を考える県民の会
秋田におけるネオニコ汚染実態の定量的解明と環境・食の安全基盤構築の県民的展開 - 城本(大野)啓子
環境DNA分析による,「世界自然遺産の島」の水田の生物多様性へのネオニコチノイド系農薬の影響評価の試み
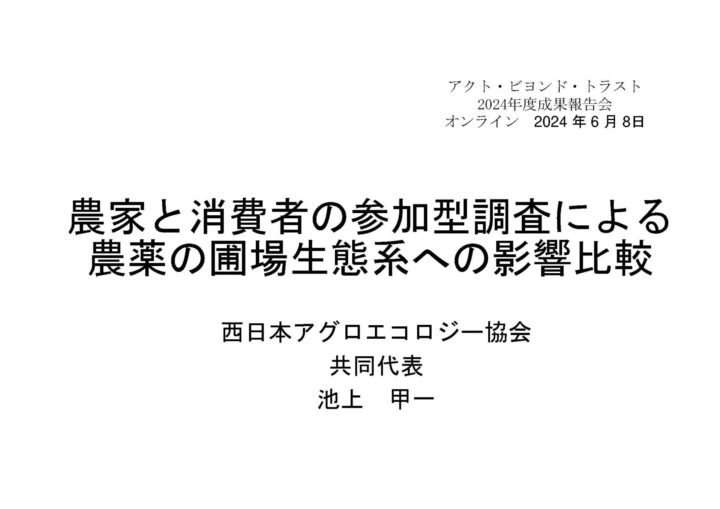
◆特定非営利活動法人・西日本アグロエコロジー協会(発表者:池上甲一)
農家と消費者の参加型調査による農薬の圃場生態系への影響比較(2024)
参加型研究の3年目
3年間の助成の報告になります。本調査の目的には2点あり、1)水田の陸生昆虫と水生昆虫を中心に生物相を把握すること、2)水田に使用される浸透移行性農薬の残留濃度を測定することです。そして、両者の関係を実証的に把握することでした。実験室の環境ではなく、実際に使用されている水田を調査することと、農家や消費者に参加してもらう「参加型研究」も特徴です。アグロエコロジー推進の基礎資料とする目的もありました[p.2]。
調査の概要
調査の枠組みは、慣行水田と有機水田で水、土、稲を採取し、田植えの前後(苗箱農薬使用時期)、出穂の前後(カメムシ農薬使用時期)の合計4回の農薬残留比較調査を行ない、同時期に水田の生き物調査をしました。詳しい調査方法は資料[p.3]を参照ください。加えて水源と排水路の農薬残留調査もしました。2024年度は水田のpHとプランクトン調査、兵庫県相生市での生き物調査ワークショップも開催しました[p.4]。
調査対象地域は兵庫県丹波市旧春日町と滋賀県高島市の2カ所です[p.5]。各水田での栽培品種や作業時期はp.6のとおりです。高島市の慣行水田ではこの年はカメムシ防除を行なわなかったので、田植え時期に使用したデジタルコラトップ(チアメトキサム)のみがネオニコ系の使用農薬になります。丹波市の慣行水田では、田植え時のルーチンエキスパート(イミダクロプリド)、7月のカメムシ防除のスタークル(ジノテフラン)が使用されています[p.6]。
ただ、2024年は7月の1か月間にほぼ雨がない上に高温状態が続き、p.7に整理した両地区に固有の要素もあり、高島市でも丹波市でも採水時期を統一できないという状況がありました。残留濃度に影響した可能性もあります。渇水によって、水生動物が生息できるような環境ではありませんでした。
高島市【生き物調査】――高温と渇水に悩まされる
高島市での生物種数の3年間の推移を見ると、2024年は全体的に少なくなっています[p.8]。高島市の生き物調査の総括はp.9のとおりです。月によって発生する害虫は異なり、有機・転換中・慣行いずれの水田でも一定数の害虫が存在します。2024年度の調査では、有機水田でカメムシ科の種数が多かったのですが、個体数はわずかです。いわゆる稲を食害するカメムシは少なく、ウンカやヨコバイが多かったです。慣行水田では水生昆虫の個体数が非常に少なかったと言えます。何よりも、高温と水不足による生態系への影響が懸念されました。
高島市【農薬残留調査】――不使用農薬が検出される謎
次に、残留農薬の推移を見ると、慣行水田ではクロチアニジンが恒常的に検出されました[p.10]。2023年のデータが欠けているのは、この年は中干後に水を入れなかったために採取できなかったからです。2023年、2024年は田植え後2回目の採水での数値が高くなっています。実際に散布するのは3回目採水の後なので、散布時期とは直結しない結果になりました。
ジノテフランは、有機水田と有機転換中の水田からも頻繁に検出されました。慣行水田では田植え前後に相対的に高濃度で検出されています[p.11]。2024年度には慣行水田でもカメムシ防除をしなかったのですが、高い濃度で検出されたことになります。蓄積の影響もしくは周辺からのドリフトの影響ということが考えられます。
この地区の特徴としては、非ネオニコ系になりますが、同様に浸透移行性という機序をもつクロラントラリニプロールが3年間、X地区の減農薬(有機転換中)の水田で継続的に検出されました[p.12]。苗箱にも使われる農薬ですが、この地区ではほぼ使用されていないので、どこから流入したのかわからず、今後も注意が必要です。
高島市の小括ですが[p.13]、とくにクロラントラリニプロールについては注目していきたいと考えています。
丹波市【生き物調査】――ため池と里山が支える生物相
丹波市の生き物調査は、慣行水田[p.14]と有機水田[p.15]に分けて整理しました。全体的に種数も個体数も多いです。徘徊性のクモが複数種捕捉されましたが、カニグモは漸減しています。地区全体として生物相が豊かであり、とくにため池と里山の影響が大きいようです[p.16]。徘徊性クモ類への農薬影響があることが考えられるほか、造網性のクモ類は有機でも慣行でも少なく、この地区では畦畔の草を定期的に刈り取って管理しているので、その影響もあるかもしれません。水生昆虫の種数と個体数は慣行のほうが若干多いという逆の結果になりましたが、有機水田の水を入れる時期が遅かったことが影響しているかもしれません。
丹波市【農薬残留調査】――高濃度のジノテフラン
苗箱に使用されるイミダクロプリドが慣行水田では毎年検出され、田植え時に増大しました[p.17]。クロチアニジンは2023年以降検出がありません。ジノテフランは高島市同様に有機でも慣行でも頻繁に検出されています[p.18]。気になるのは、2024年7月27日の慣行水田で、117,990pptという非常に高濃度の検出があったことです。7月20日にスタークルを散布している影響かと思います。
丹波市水田の水源はため池です。2023年は出穂前までジノテフランが検出されましたが、2024年は非検出でした[p.19]。カメムシ防除に使われる農薬なので、前年のものが残留していたようです。
丹波市の調査をまとめると、水田でのジノテフラン検出は2024年が最も高濃度でした[p.20]。水不足のため、一度使ったため池の水を再度ポンプで汲み上げて再利用し、貯水量が減少したこともあって、濃縮効果が生じたことが考えられます。イネからの検出がこれまでありませんでしたが、2024年度は微量ながら検出されました。
疑問点――カメムシ対策に意味はあるのか?
まず、イネから検出がほとんどなかったという結果について、イネに移行していないのであれば、農薬を使用する意味もないわけです[p.21]。また、高島市では2024年には高温のため、カメムシ防除よりもいもち病対策を優先しました。米の等級に関わる斑点米対策ということでカメムシ防除をしていたわけですが、重点が変わるのであれば、今後の必要性を検討してもよいかもしれません。もう1点気になるのは、クロラントラリニプロールの侵入経路が不明であったということです。
次に、中干について。一昨年も問題にしましたが、中干の徹底と長期化がメタン排出減のためによいとして、政策誘導によって推奨されていますが、水田の大規模化に伴う品種分散と併せて、生き物調査がしにくくなる原因となっています。いっぽうで、中干の時期が地域によって異なると、生き物の逃げ場となる可能性もあります[p.22]。降水パターンの変化と高温継続の影響も考慮が必要になってきました。この3年間での調査の発見としては、昆虫類の減少と農薬残留の明確な因果関係は得られず、それよりもむしろ周辺の環境が重要であるという結論に至りました。p.23~24の模式図を見ていただければわかるかと思います。
まとめ――生物多様性を指標にしたコメの可能性
最後に、アグロエコロジーの観点から、2023年に環境保全米への支払い意思額について調査しましたが、生物多様性について知識があるグループとそうでないグループでは明確な差異が生じ、知識があるグループは「コウノトリ米」よりも「ホタル米」のほうに高い支払意思額を示しました[p.25]。つまり、コウノトリのような「ビッグネーム」以外でも、生物多様性への知識があれば、高い支払い意思額を持つことができると言えそうです。
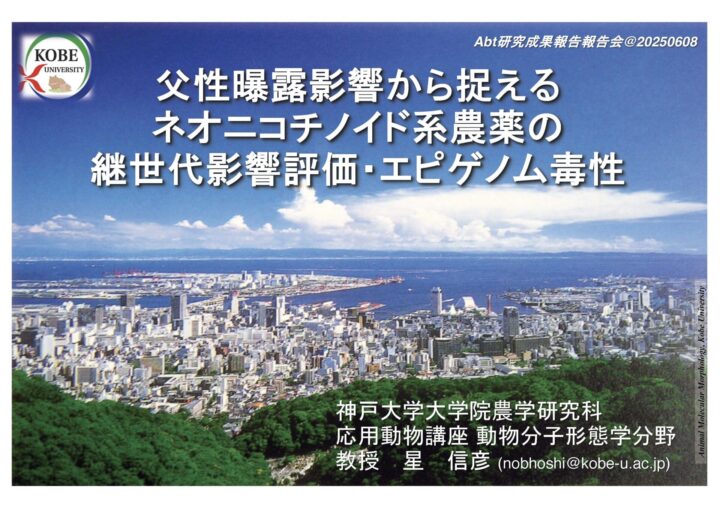
◆神戸大学大学院 農学研究科 動物分子形態学分野 星研究室(発表者:星 信彦)
父性曝露影響から捉えるネオニコチノイド系農薬の継世代影響評価・エピゲノム毒性
背景と目的
ネオニコチノイド系農薬(ネオニコ)は、国が定義する無毒性量であっても、哺乳類に対して神経・生殖・免疫毒性を示すことが多数報告されています。私たちもこれまでに、母親が妊娠中にネオニコを摂取した場合、その子孫の神経発達に世代を越えて影響が及ぶことを報告してきました(4世代実験)。
一方、2020年頃より、父親の環境要因とその子どもの疾患リスクとの関連を示す研究報告が増加しています。たとえば、父親の「うつ」「肥満」「老化」「有害物質」がその子どもに影響する。すなわち、受精前の精子の状態が子孫の疾患リスクに影響を与えるという考え方が支持されるようになってきたのです[p.4]。その中には、有機フッ素化合物(PFAS)などの有害物質を父親が摂取すると、その子どもの肝臓や脂肪組織に変化が生じるという例もあります[p.5]。このように、父親の「非遺伝的」な要因――すなわち環境要因――が世代を超えて影響を及ぼすメカニズムとして、「精子エピゲノム変異」※1が有力視されています。
※1:エピゲノム変異:DNA配列そのものの変化を伴なわずに、遺伝子の発現を変化させる機構。DNAメチル化、ノンコーディングRNA、ヒストン修飾の変化などが関与する。
現在のところ、父親がネオニコを摂取した場合の次世代影響についてはほとんど検証されていません[p.6]。父親への曝露では、精子を介して影響が伝達されると想定されるため、母親の曝露とは異なるメカニズムによって次世代に影響を及ぼす可能性があります。
私たちの細胞では、DNAという設計図からメッセンジャーRNAが転写され、それが翻訳されてタンパク質が合成されます。マイクロRNAとは、このメッセンジャーRNAに結合することでその翻訳を抑制し、遺伝子発現を制御する小さな非コードRNAの一種です[p.7]。
実験の方法――マウス2世代による影響調査
そこで、本研究では、ネオニコの一種クロチアニジンを父親マウスに摂取させ、生まれてきたF1世代(子=次の世代)に対して、行動試験、メッセンジャーRNA解析、脳組織のモノアミン解析、血漿中のホルモン解析を行いました[p.9]。さらに、クロチアニジンを曝露したF0世代(父親)マウスの精子マイクロRNAを解析し、次世代影響との関連を調べました。
試験に使用した動物は、父親マウスおよびそのF1雄産子です[p.10]。投与群の父親マウスには、無毒性量のクロチアニジンを9週齢時より6週間摂取させました。15週齢時にクロチアニジン非曝露メスと交配させ、その後精子を採集しました。作製したF1雄産子の対照群と父親曝露群は通常条件下で飼育しました。
行動試験と海馬RNAシーケンス解析の結果
結果です。F1世代の行動試験の結果、父親曝露群では、オープンフィールド試験[p.12]および高架式十字迷路試験[p.13]において、自発運動量の有意な減少が確認されました。さらに、モノアミン神経伝達物質のうち、ドーパミンおよびヒスタミンは海馬(記憶・空間学習の司令塔)において減少傾向を示し、線条体(運動・意志決定・学習の制御)では有意に減少しました[p.14]。ドーパミンは神経伝達物質のひとつで、運動・快感・意欲・学習・注意・ホルモン調節など多くの生理機能に関わります。ヒスタミンは私たちの体内に存在する生理活性物質で、主に免疫反応やアレルギー反応、胃酸分泌、神経伝達などに関与しています。
F1世代の海馬RNAシークエンス解析によって、合計381個の発現変動遺伝子が同定されました[p.15]。発現低下遺伝子148個について、生物学的機能に関するエンリッチメント解析を実施しました。p.15に、有意に抑制されると予想された上位5つの機能を示しています。父親曝露群における発現低下遺伝子は、神経系の細胞、ニューロンやシナプス、神経突起形成に関連することが示されました。また、パスウェイ解析では、カルシウムシグナルやシナプス形成シグナルの抑制、軸索誘導への影響が予測されました[p.16]。
マイクロRNAの関与とF1海馬の発現遺伝子
以上の結果から、クロチアニジンの父親曝露は、次世代の行動および神経系に影響を及ぼすことが示されました[p.17]。そのため、この父親曝露のメカニズムについて、精子マイクロRNAの関与の可能性を検討することとしました[p.18]。
精子マイクロRNAシーケンスの結果、対照群と投与群との間で2倍以上の増減を変動の条件としたところ、35個のマイクロRNAが同定されました[p.19]。増加したマイクロRNAについて標的予測を行った結果、122個のメッセンジャーRNAが同定されました[p.19]。これらの遺伝子は、細胞内情報伝達ネットワークであるMAPキナーゼカスケードや、軸索誘導、神経系の発生に関するパスウェイに多く含まれていました[p.20]。
精子マイクロRNAとその子どもであるF1世代の海馬の発現遺伝子を統合したネットワーク図を作成しました[p.21]。赤いシンボルは増加したマイクロRNA、緑のシンボルはF1海馬における発現低下遺伝子を示しています。この図からは、miR-149-5p、295-3pによる神経突起形成や神経細胞発生への影響が強調されました。
考察――クロチアニジン摂取は次世代の行動と神経系に影響を及ぼす
クロチアニジンを摂取した父親マウスの精子においては、マイクロRNAの量が変化しました。増加したマイクロRNAは、MAPキナーゼカスケード、軸索誘導、神経系の発生に関する遺伝子群を標的とすることが示され、miR-149-5p、295-3pの役割が強調されました。miR-290から295のクラスターは、4~8細胞期での発現増加が報告されており、胚発生初期における細胞周期に関連する役割を持つことが示唆されています。そのため、クロチアニジンの摂取により変動したマイクロRNAは、胚発生における遺伝子発現の調整に関与する可能性が示されました[p.24]。
結論として、本研究では、クロチアニジン曝露によって精子マイクロRNAの量が変化すること、そして次世代の行動および神経系に影響を及ぼすことが明らかになりました。さらに、精子マイクロRNAの変動はクロチアニジン父親曝露評価のメカニズムの一つであることが想定されました[p.25]。
これまで5年間、abtの助成を受け、ネオニコチノイド系農薬の哺乳類への影響を調べてきました。本年度はその集大成であり、この農薬には新たな毒性のあることがわかりました。すなわち、一つは精子や卵子を介するエピゲノム毒性、二つ目として胎児期の環境の影響、三つ目としてエピジェネティックなリセットと伝達の仕組みです。エピゲノム毒性とは、後天的に獲得されたエピゲノム変異が遺伝的変異を伴わずに次世代に受け継がれる現象であり、獲得形質の遺伝という概念とも関係していることが明らかになってきました。
結語――エピゲノム毒性でわかった環境中微量化学物質の問題
化学合成農薬が一般に使用されるようになって、およそ70年が過ぎました。人類はようやく農薬の本当の姿を理解できるようになってきたのではないでしょうか。一般に胎子および新生子は成体と比べて化学物質等への感受性が極めて高く、ヒトでも非可逆的に脳・生殖機能、さらには胸腺・腸管免疫系を障害することが示唆されています。
環境中微量化学物質の作用メカニズムの解明は、分子生物学的知見をもとに新しい時代に入ったといえますが、器官形成・発達時期である胎子・新生子期での曝露が、長期にわたって非可逆的にフィードバック機構の破綻を招来する作用機序には未だ不明な点が多くあります。
さらに近年、細胞世代を超えて継承され得る、塩基配列の変化を伴わない遺伝子発現制御について研究する新たなパラダイムとして、エピゲノム毒性の領域が提唱され、環境中微量化学物質が生物に及ぼす環境エピゲノムの展開が必須となっています。「環境汚染と健康」の問題は未来、すなわち次世代に先送りしてはならないし、「疑わしきは罰せず」ではすまされません。農薬とのつきあい方を真剣に考えるときが来たと思っています。
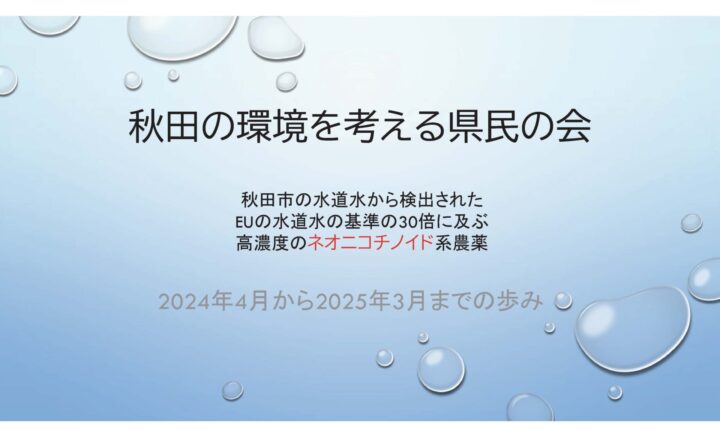
◆秋田の環境を考える県民の会(発表者:近藤 正)
秋田におけるネオニコ汚染実態の定量的解明と環境・食の安全基盤構築の県民的展開
秋田市の水道水汚染を受けて始まった活動
2024年度4月に採用され、調査・研究、広報社会訴求、市場“緑化”の3カテゴリーで市民の皆さんと活動しています。これまでの取り組みは小冊子にまとめていますが、それを元に報告します。
発足の経緯を説明します。2022年に秋田市の水道水から886pptのジノテフランが検出されました。その翌年、水道水の残留検査を実施しようということになり、2023年には秋田市の水道水から3,060pptのジノテフラン、510pptのスルホキサフロルを検出しました。そこで、県や市に調査の実施や水道水の浄化を訴えようと活動しています。
市民を巻き込んだ取り組み
秋田県は、7万ヘクタールほどの水田を持ち、県面積の15%が水田になっています[p.2]。秋田市水道の取水源は、この大水田地帯を流れる雄物川(おものがわ)の下流部にあります。今回、秋田市のほかに、この雄物川流域全体での汚染を把握したいと思っております。そのほかに、市民向けの出前講座や学習会を行ない、有機農産物を県民が求める条件を把握しつつ、有機生産者から課題の聞き取りなども行なっています[p.3]。
市場“緑化”としては、耕作放棄地が増えており、残った農地の大規模化が農薬の多用にもつながっています。そこで、市民自身でも休耕地を借りて有機農業に挑戦することをスタートしています。その結果、「自分たちもやりたい」という人が増えており、貸したい農家さんとつなぐことも進めています[p.4~5]。
講師を招いた講演会の実施
小規模な勉強会は、『静かな汚染――ネオニコチノイド』の上映会をはじめ7回実施しました[p.6]。大きな勉強会は、星信彦先生に秋田にお越しいただき、「ネオニコチノイドとは?」という根本的な講演をいただいています[p.7]。
前向きな話題としては、オーガニック給食を秋田県内にも広めようということで、給食無償化運動をしている団体ともジョイントし、千葉県いすみ市の鮫田晋氏を招いて先行事例の講演会を開きました[p.8]。こちらは秋田県立大学、秋田市議会、男鹿南秋地区7つの市町村や教育委員会の後援も得て、200人ほどの参加をいただきました。ネオニコの汚染実態も紹介しています。
水道水測定結果の公開
水道水などの測定結果は、生データをウェブサイトで公開しています。秋田県にある3つの一級河川の下流にある3市(秋田市、能代市、由利本荘市)の水道水などとともに、河川水、地下水、名水百選などの測定結果になります[p.9]。汚染の常態化が懸念されています。農薬を散布する夏だけではなく、冬場でも測定されるのは、地下水が汚染されているからだと推測されます。この結果については、2025年9月に秋田で開催される水文・水資源学会のほか、農業農村工学会でも報告する予定です。
引き続き、これまでできなかったアンケートや有機給食無償化自治体への聞き取りなども強化し、秋田県民の認知度を高めていきたいと思っています[p.10]。
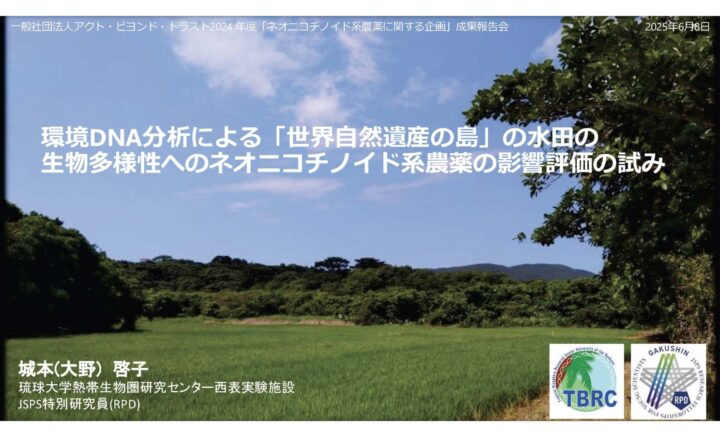
◆城本(大野)啓子
環境DNA分析による,「世界自然遺産の島」の水田の生物多様性へのネオニコチノイド系農薬の影響評価の試み
研究の背景――世界自然遺産エリアで水田の多面的機能を守るために
世界自然遺産にも登録されている地域で、ネオニコチノイド系農薬の水田への影響について、環境DNAによって生物多様性評価を行なう新しい試みになります。水田は、単にコメをつくる場所というだけではなく、地下水を貯めて浄化し、たくさんの生き物の生息地となるといった重要な機能を持っています[p.2]。農村の景観保全や、沖縄でいえば大綱引きの藁を提供するといった伝統文化の継承にも寄与し、子どもたちが生き物に触れる教育の場でもあります。今はなくなりつつある湿地に代わって、こうした多面的機能を担う水田をどうしたら守り、持続可能な場所として活用し続けられるのかという問題意識が本研究の背景にあります。
今回対象とした沖縄県八重山地域は、県の7割を占めるお米の産地です[p.3]。日本の水田全体から見ればわずかな面積ですが、世界自然遺産登録地に隣接する重要な場所です。カンムリワシのような希少生物も田んぼを利用していることが知られていて、農業利用と自然保全のバランスが求められる地域です。このようなエリアにおいて、農薬の影響を正確に把握することは急務になっています。
研究の目的――環境DNA分析の有効性をテストする
本研究の主な目的は二つあり、一つは環境DNA分析という手法がネオニコチノイド系農薬の生物多様性への影響評価に関して有効であるかテストすることです。もう一つは、サンプリングの時期やPCRプライマーの種類といった手法面での検討を行ない、より信頼性の高い分析を実現するための基礎データを得ることです[p.4]。
環境DNA分析とは、水の中に溶け込んでいる生物の痕跡のDNAを調べる技術です[p.5]。もともとは、海水中の魚の種類を調べる方法として活用されていましたが、最近では昆虫や爬虫類などほかの生物にも適用されています。水の中に溶け込んでいる糞や皮膚、体液などのDNAを採取して、生息している生き物を特定します。
方法は二種類あり、一つは標的種のDNAをピックアップして増殖して調べる方法で、コロナのPCR検査と同じです。もう一つは、採水した水に含まれる昆虫や魚のDNAを、PCRプライマーセットを使って網羅的に増幅させて調べる方法で、環境メタバーコーディングと言います。今回使用したのは後者の技術で、生物を捕まえる必要がなく、生物が見えなくてもDNAの痕跡さえあれば検出できることが利点です[p.6]。水を汲むだけで一度にたくさんの生物種を調べられるので効率的です。
調査方法――慣行水田と農薬不使用水田を比較
今回の調査方法は、石垣島内の水田地域3か所を調査地とし、採水できない場合に備えて2か所を予備の調査地としました。ジノテフランを散布している慣行水田と、対照として農薬不使用の水田を設定し、それぞれで調査を行ないました[p.9]。
事前にジノテフランの散布日を聞いておき、その1週間前に1回目の採水を行ないました。その後、散布1週間後に2回目の採水、さらにその1週間後に3回目の採水を行ないました。散布農薬はスタークルやビームといったジノテフラン混合剤で、ラジコンヘリで4メートルの高さから散布していたという情報を得ています。1か所は人手によるスタークル散布でした。斑点米対策としての散布という情報です[p.10]。
サンプリングの手順ですが、水田への流入口から出水口の間に、流れが溜まる水尻があります。その近辺で10か所、200ミリリットルずつひしゃくで採水し、バケツに集めて1リットルずつパックして保冷して研究室に持ち帰ります[p.11]。採取した水を注射器状の器具で吸い取り、ろ過材の入ったステリベクスフィルターというフィルターに通して、DNAを中に吸着させます[p.12]。これを冷凍保存し、DNAを抽出して、PCRとライブラリ調整で増幅して検出します。
結果と知見――見えてきた課題を踏まえて研究継続中
農薬散布後1週間と2週間後、とくに2週間後のサンプル[p.13、緑の線]からのDNA抽出量が農薬の使用・不使用に関係なく低下しており、プライマーによる増幅量が少ないことがわかっています。今ちょっとこちらの調整を行なっております。
この研究で得られた知見です。今回は田んぼの水を濾過する際に、フィルターがすぐに詰まってしまいました。1リットルくらいを濾過する予定が、250~500ミリリットルくらいしかフィルターで濾過できなかったので、ツールを変えて濾過量を増やす実験を行なっています[p.14]。
農薬の検出状況についても、今回は使用農薬の聞き取りのみで実際の濃度は調べていないのですが、農薬の使用・不使用にかかわらずDNAの検出量が減ってきているので、何かが影響しているかもしれないということがわかってきました。
また、今回はプライマーのDNA情報を参照したのですが、メタバーコーディングをするためには昆虫のDNA情報がとても大切です。プライマーで増幅できる領域のデータについて、八重山に生息する昆虫に該当するものがとても少なかったため、現在、殺虫剤の影響を受けやすいと言われるゲンゴロウのほか、八重山でよく見られる水生半翅類を含めた主要な水田昆虫類のデータベースを作って、プライマーとの調整を行なっています[p.15]。
今後の課題として、農薬使用実態や検出濃度と生物多様性の関係を正確に明らかにしていきたいと思っています[p.16]。農業者への情報提供や減農薬への技術開発はいろいろ言われていますが、ネオニコフリーの政策はあまり進められていないので、環境保全の政策支援として、今回の実験結果をいろいろなところに知らせていきたいと思っています。2025年度は農薬の検出状況も調べて、今回のDNAデータを拡張して対照していきたいと思っています。まだ試行段階で途中ですが、将来的には地域と連携した持続可能な農業のあり方に寄与できると考えています。
全参加者による座談会と会場との質疑応答
クロラントラリニプロール流出源、イネの検出について(西日本アグロエコロジー協会)
宮田委員:池上さんに質問です。クロラントラリニプロール検出の原因ははっきりしないとのことですが、散布農薬の中に含まれていなかったということでしょうか。
池上:クロラントラリニプロールは最初2022年に検出され、「これはいったい何なんだろう」と調べると、最初は果樹や野菜に使用される農薬ということでした。近くには家庭菜園くらいしかないので、それが流入源だとすると、ちょっと濃度が高いと思っていました。さらに調べると、最近になって水稲の苗箱に使用されることがわかりました。
しかし、このX地区の農協からこの苗箱農薬を購入している農家さんはいませんでした。入り作で委託している大規模経営の農家さんも、全員に聞いたわけではありませんが、インタビューすると、この地区は低農薬地帯で、3分の2くらいが滋賀県の環境保全型稲作の登録地域になっています。従って農薬は使いにくく、作っているのも品質をあまり考えなくてよい飼料米なので、除草剤は使うが農薬はあまり使わないということでした。
だとすれば、苗箱農薬も使わないような地域に限って、このクロラントラリニプロールが多く継続して検出される理由がわかりません。シロアリ対策にも使われるそうですが、その場合は高濃度で使用するので、圃場の横にある別荘地から浸透してきている可能性も皆無ではありません。機会があれば調べていきたいと思っています。
星:クロラントラリニプロールというのは「ポストネオニコ」と呼ばれる農薬です。飛翔目、カメムシやバッタ類も対象で、殺虫スペクトルが非常に広いのが特徴です。昨年、宮古島で調査したところ、地下水からEUの基準値の1.8倍という高濃度で検出されました。現在、ネオニコへの懸念が高まっていることから、農薬会社はポストネオニコ系へとシフトしており、クロラントラリニプロールはその代表格です。この農薬は、昆虫の筋肉におけるカルシウム放出機能を制御して麻痺させる作用機序を持ちます。神経伝達系には作用せず、成長抑制や筋肉麻痺を引き起こすため、一般には毒性値が低いと言われています。しかし、私たちが過去3年間にわたって動物実験を行なったところ、筋肉よりもむしろ神経系に影響がみられました(doi: 10.1292/jvms.23-0041)。宮古島も同様でしたが、国内の他地域でも水道水中から相当量が検出されています。池上先生のご発表にあった、「イネから検出されない理由がわからない」という結果も気になります。
池上:イネから出ないというのは検出限界値の問題かもしれないと思っています。一般的にイネも土もppmの単位で見ていますが、水はpptで、単位が違いますので、そのへんの影響があるかもしれません。それにしても、それまであまり出なかったのが、去年ちょっと出たというのがなぜかはよくわかりません。これがもし続くようであれば、そもそも散布の必要があったのか、ということになります。
実験対象農薬の選定について(神戸大学 星研究室)
安田委員:星先生に質問です。クロチアニジンのオス精子に対するエピジェネティックな影響ですが、ネオニコの中からクロチアニジンを対象に選んだ理由を教えてください。
星:農薬の年譜を見ると、イミダクロプリド(1991年登録)、ニテンピラム(1995年登録)、アセタミプリド(1995年登録)、チアメトキサム(1998年登録)、チアクロプリド(2000年登録)と続き、その後にクロチアニジン(2001年登録)、ジノテフラン(2002年登録)が登場しています。
私たちがネオニコの研究を始めた十数年前には、イミダクロプリドやアセタミプリドの毒性に関する研究はすでにたくさん発表されていましたが、最後発のクロチアニジンとジノテフランについての報告はほとんどありませんでした。また、長年にわたり佐渡市でトキの繁殖障害の原因について研究していましたが、その佐渡で最も使用されていたのがクロチアニジン(商品名ダントツ)とジノテフラン(商品名スタークル)でした。そうした背景から、稲作で広く使われている農薬としてクロチアニジンを研究対象として選択しました。
ついでに申し上げると、先ほど秋田県におけるスルホキサフロルの使用について言及がありました。前述7種のネオニコチノイドにはすでに問題提起がなされていますが、それに代わる類似化学物質の登場は“いたちごっこ”の様相を呈しています。「ネオニコフリー」と称しつつ、類似作用機序を有するスルホキサフロル(商品名エクシード)、フルピラジフロン(商品名シバント)、フルピリミン(商品名エミリア)といった農薬が、食品に使われています。しかし、これらはいずれもネオニコ同様、ニコチン性アセチルコリン受容体に結合する神経毒性農薬であり、「ネオニコ類似農薬」と位置づけられます。
さらに問題なのは、これらの類似農薬はすべて有機フッ素を含有しており、PFASとの類似性が指摘されている点です。秋田の事例でも明らかになったように、現在の農薬使用は、このようなPFAS農薬へとシフトしつつあります。これまでPFAS問題と農薬問題は別個に議論されてきましたが、これらのPFAS農薬が広く使用されるようになると、その境界は一気に曖昧になります。ネオニコは、動物実験においては1日程度で体外に排出されるのに対し、PFASは難分解性であり、体内に年単位で蓄積します。発がん性をはじめとする多様な健康影響が懸念されています。ネオニコは主に神経毒性を示すものの、発がん性は確認されていません。しかし、ネオニコに代わってこれら新しいPFAS農薬が使用されるようになれば、今後は農薬によるPFAS汚染という新たな問題が生じる可能性があります。この点については、まだ十分に知られていないのが現状です。
水道水の汚染除去、自治体の対応について(神戸大学 星研究室)
会場:水道水から農薬を取り除くことは難しいのですか?
星:まずは、お住まいの地域で、水道水がどこでどのように浄化処理されているかを調べてみてください。オゾンによる殺菌と活性炭処理を行う「高度浄水施設」では、農薬は8~9割程度が除去されます。しかし、このような処理工程を持たない従来型の浄水処理だけでは、農薬やPFASを十分に取り除くことはできません。現在では、日本全国どこでも、水道水から20種類以上の農薬が検出されていますので、私は、一般家庭でも浄水器の使用は必須であると考えています。高価な製品である必要はありませんが、活性炭フィルターと逆浸透膜フィルターの両方を備えたタイプをお勧めします。単なる中空糸膜フィルターだけの製品では農薬やPFASは除去できません。迷ったら、「PFAS、PFOA除去可能」などの表示のある製品を選ぶといいと思います。また、使用期限や濾過流量を守り、定期的にカートリッジを交換することが非常に重要です。これについては、共同研究者の北海道大学の池中良徳先生によっても確認されています。
会場:ネオニコチノイドの危険性を自治体は認識して対応を取っていますか?
星:秋田での水道水からの検出について、「国の基準値を大きく下回る」という報道がありましたが(『秋田魁新報』2024.6.21)、EUの基準値(100 ng/L)※2に対し、日本の基準値(600,000 ng/L)は6,000倍も高く設定されています※3。基準値に対する国の対応は、最新の知見を無視していることになります。
※2:EUの水道水中の農薬の基準は一律0.10 μg (=100 ng)/L
Directive (EU) 2020/2184 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2020 on the quality of water intended for human consumption (ANNEX I: Minimum Requirements for Parametric Values Used to Assess the Quality of Water Intended for Human Consumption)
※3:日本の水道水中での農薬は水道水質の基準項目には入っておらず、「水質管理目標設定項目」とされており、個別の農薬ではなく、検出された農薬の総量を「目標値」と比較するという複雑な方式を採用している。個々の農薬は検出の可能性が高い「リスト掲載農薬類」、検出状況の収集に努めるべき「要検討農薬類」、浄水から検出される可能性の低い「その他農薬類」等に分類されている。秋田の事例で言及されているジノテフランは「その他農薬類」に分類され、その目標値は0.6 mg (=600,000 ng)/Lとされている。
環境省 水道水質基準「農薬の考え方について」
環境省 水道法関連法規「水道水質管理計画の策定に当たっての留意事項について」
つまり、国の対応は、基準値を高く設定しておいて、農薬が検出されても「基準値以下だから問題ない」とするものであり、実質的には安全性を担保しているとは言い難い状況です。有害化学物質の排出量を管理するPRTR法(化学物質排出移動量届出制度)においても、その対象物質の約3分の1が農薬として使用されているにもかかわらず、農地からの排出量については届け出義務が課されていません。そのため、この制度は農薬に関しては実行性を欠いた、まったくの“ザル法”と化しているのが現状です。これは農薬問題に限らず、国の政策全体が企業寄りであることを示す一例であり、多くの皆さんも、それを強く感じておられるのではないでしょうか。
精子曝露の孫世代への影響について(神戸大学 星研究室)
宮田委員:オスの遺伝子のF1世代への影響は、F2世代にも波及することが推測できるでしょうか。
星:研究が遅れており、F2(孫世代)についてはまだ調べていませんが、ニコチンやグリホサートの場合、このようなエピゲノム毒性は子ども世代、孫世代、ひ孫世代に影響を及ぼすことがわかっています。タバコのニコチンは、ネオニコと同じくニコチン性アセチルコリン受容体に作用するので、ネオニコでも同じことが起きるのではないかと考えています。
暴露期間と影響、雌雄差について(神戸大学 星研究室)
会場:ネオニコチノイドの精子へのエピジェネティックな影響には、どれくらいの曝露期間を要し、また曝露期間からウォッシュアウト期間があると影響がなくなるのでしょうか?
星:マウスに摂取させた6週間という期間は、精子が作られる期間に相当します。これは人間も同様であり、毎日残留農薬を含む食品を摂取していれば、継続的な曝露が続くことになります。そのため、オーガニック食品を選んで体内をきれいに保つことが非常に重要だと考えています。北海道大学の池中先生の研究によれば、1ヵ月間オーガニック食を続けることで、体内から農薬が検出されなくなるという結果が得られています(doi: 10.1016/j.envint.2022.107169)。ネオニコは水溶性なので、体内からは比較的速やかに排泄されます。従って、とくにオス動物においては、精子が作られている期間に農薬を摂取しないことが重要になりますね。
会場:ネオニコチノイドが雄性マウスに影響が強い理由を教えてください。
星:今回の実験は、オスの精子に対する影響を評価する目的で実施したものですが、過去に雌雄差を比較した研究では、オスのほうがこの農薬の影響を受けやすいことが明らかになっています(doi: 10.1016/j.taap.2022.116283)。たとえば、オスでは体重の増加がみられますが、これはエストロゲン受容体と関係している可能性があります。具体的には、脳の視床下部弓状核でのエストロゲン受容体α発現細胞が雄のみ増加します。また、ネオニコによる地下水汚染が懸念される宮古島では、小学生男子の肥満が増えているという報告があり、ネオニコの影響が示唆される事例と考えています。
さらに、学習能力や神経影響に関しても、メスではほとんど影響がみられない濃度でも、オスには明らかな影響が認められます。このように、ネオニコの影響には明確な雌雄差が存在すると私たちは考えています。
カメムシ捕獲数への影響、カメムシの種類について(西日本アグロエコロジー協会)
城本:池上先生に質問です。昆虫種数と濃度との関係があまり見られなかったとのことですが、斑点米カメムシのスイーピング捕獲数にも影響はなかったのでしょうか。
池上:稲作に影響を与えるカメムシは、3年間を通じてそれほど捕捉されませんでした。これはやはり畔の草刈りを徹底しているところでは、あまり見つかりません。若干放っておいているようなところでは見つかります。逆に、手が回らずに畔の草が繁茂してしまっているようなところになると、またカメムシは出にくくなり、他の昆虫も出にくくなります。周辺にカメムシの付きやすいマメ科の植物などがたくさんあれば、そこから飛来することもあるかもしれませんが、幸い周辺に耕作放棄地が少ないということもあり、そのような影響はなかったのかもしれません。
カメムシ対策については、農薬の影響よりも周辺環境や畔の管理の程度や、草を刈る時期が影響するようです。クモが産卵する禾本科の植物を10~15㎝に高刈りしておき、孵化期に刈り取ると孵化したクモが田んぼに入ってカメムシを食べてくれるという方法を実践している人もおられます。そのような耕種的な工夫をしていると、実際の害が少ないと思われます。
水性昆虫に関しては、田んぼの中の植物の植生の影響も受けていそうですが、今回の企画には植物生態を専門とする方が加わっていないので、よくはわかっていません。
安田委員:それに関連して、去年からコメの収量が少なくなっていることの原因は、これまでの斑点米カメムシとは別種の、イネカメムシという昆虫が全国的に大発生したことで、稲穂が十分に熟さないという現象があったと聞いています。今後、そのイネカメムシを対象に農薬の大量散布が推奨されることが懸念されるのですが、イネカメムシの繁殖状況はいかがでしょうか。
池上:高島市も丹波市も、カメムシの発生量はそれほどではありません。果樹、茶、野菜はカメムシの被害に遭っていると聞きますが、イネはあまりない状況です。しかし、県は予防的に撒くことを推奨しています。
有機水田での農薬検出経路について(西日本アグロエコロジー協会)
星:池上先生に質問です。有機水田で検出されたジノテフランの由来は調べられたのでしょうか。
池上:この地区は琵琶湖から逆水灌漑(揚水ポンプを使った農地への水供給)をしていて、慣行水田と同じ管路を使っています。そこの水を調べたところ、慣行水田からの水は若干高めでしたが、有意差があるというほどではありませんでした。
ポストネオニコ農薬の使用について(秋田の環境を考える県民の会)
星:近藤先生に質問です。ご提示いただいたデータでは、7種類のネオニコが検出されるところと、スルホキサフロルやフルピリミンといった農薬が高率で検出されるところに分かれているようですが、これはどのような違いがあるのでしょうか。JAが指導しているのでしょうか。
近藤:秋田は基本的には県が指導しています。スルホキサフロルも県が推奨しています。雄物川の上流・中流・下流で8月に取ったデータでは、上流で少し高く、水田の比率が高い地域で直接汲んだ水では、エチプロールも含め、農薬14種すべてで1,000 pptを超えていました。秋田県は、国の方針に従っていると言っています。
沖縄県内での農薬使用状況について(城本(大野)啓子)
星:宮古島での汚染例はご存知かと思いますが、沖縄県内でも島によって農薬の使い方は異なるのでしょうか。
城本:違うと思います。全県でサトウキビに転換されているので、そこで使われているフィプロニルが問題になっています。宮古島の場合、川ではなく地下水系を使っているので、そこへの残留は問題が大きいと思います。
星:沖縄県ではサトウキビ栽培を宮古島に依存していて、もともとは3割ほどだった栽培面積が、現在では8~9割を占めるようになっているため、虫の住む場所が減少し、その結果、密度が高くなっていると聞きましたが、実際のところはどうなのでしょうか。
城本:石垣島でも西表島でもサトウキビは栽培されていて、特産になっています。宮古島と比べると規模は小さいと思いますが、それでも水田から転換されていると思います。サトウキビ畑からの赤土の流出とともに、海でも検出されているという報告を聞いています。
星:宮古島ではカニもいなくなってしまったと聞きました。
城本:甲殻類にも影響が出ているというような生物多様性指標の話も聞いているので、気にしているところです。
発表者から最後に一言
城本:今回、水田を調査に使わせていただいたので、農家や地域の方と話をする機会がありましたが、ネオニコチノイド農薬のことが心配だという方もいれば、あまり詳しくないという方もいました。結果を含め、いろいろな方に伝えていきたいと思っています。石垣市、沖縄県、環境省と関わることもできたので、西表島・石垣島という世界自然遺産の島で使っている農薬であると情報提供することで、県や国に訴えていけるのではないかと思っています。
県民の会・近藤:市民の皆さん主体での取り組みであることが良いと思っています。昨今、学術会議の骨抜きが議論されることなども、真実を見抜こうとする市民の取り組みを阻害する動きと重なるのではないかと思っています。ネオニコだけでなく、コメの問題、こまちRの問題もそうです。秋田はそのような中で、がんばらなければいけません。星先生はじめ、皆さんと一緒にがんばっていきたいと思います。
県民の会・伊藤:私はこの団体でSNS発信を担当していますが、2024年よりも2025年に入ってから、一般の方が発信をシェアしてくれるようになってきて、周りが変わってきたな、と思っています。興味のなかった人が興味を持ってくれるようになったな、と肌で感じています。引き続き、コツコツ発信していきたいと思っています。
神戸大学・星:この5年間助成をいただき、ありがとうございます。いろいろな方とコミュニケーションする機会ができ、お子さんを抱えて地道な活動をされているお母さん方を知ることもできました。私は国会で3回ほど話をしていますが、国と企業との結びつきは強く、国はなかなか変わらないんだと思っています。
私自身も、この研究をするまで、農薬についてはそんなに詳しくなかったのですが、動物を使って試験すればするほど、農薬の影響はこんなにも大きかったのか、と日々実感しています。もう間違いなく、農薬というのは毒なんですね。だから何とか、農薬を使わない方向に行けばと思っています。
しかし、国が変わるのを待っていては、何十年かかるかわかりません。私がいつも講演で話しているのは、「オーガニック食品を食べる人」が国民の5%、10%になれば農業政策も変わってくるのではないか、ということです。そうでなければ、ネオニコが使用禁止になっても、その後にもさらに毒性の強いポストネオニコ農薬が出てくるだけなんですね。実際に日本各地でそのようないたちごっこが行われています。農薬メーカーはとにかく日本に農薬をたくさん使わせたいわけですが、それをわれわれが防いでいかないと、子どもたちの脳を含めたさまざまな健康影響も進んでいってしまいます。今後もがんばっていきたいと思います。
西日本アグロエコロジー協会・池上:3年間ありがとうございました。農薬の化学については素人だった私がたくさんの方にお世話になりながら勉強してきて、いちおうは説明できるようになりました。これまでの農薬分析は、結局、農民連食品分析センターにお願いしてきました。近藤さんのところもそうだと思いますが、どうも分析委託が集中しているようです。なので、複数の生協さんとかが資金を出し合って、市民型・消費者主導型の研究所のようなものを作っていくことが必要なのではないかと強く感じているところです。市民参加型の調査研究の態勢や仕組みを作っていくことに、自分も努力していきたいと思っています。
今年はオーガニックビレッジ宣言をした丹波市の市役所から予算を得て、調査を継続しています。高島市は協議中とのことですが、こちらも可能性はあるかもしれません。国が変わるのは大変ですが、市町村レベルで変えていくことが大事だと思っています。3年間継続して、暑い中、田んぼで虫を捕ったりしていると、農家さんも「何をやってるんだ」と声をかけてくれるようになったりしました。そこで話をすると向こうの考え方もわかるし、こちらの活動も伝わります。実践を続けていくのが大事だと思いました。夏の高温の中での作業になるのですが、これからも生態系への影響を見ていきたいと思っています。